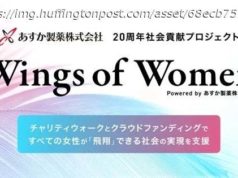Array
米国のネットストリーミングサービスの形態として、「FAST」と呼ばれるものが急速に拡大している。FASTとは、「Free Ad-Supported Streaming TV」の略で、無料で広告を入れてコンテンツをライブ配信するサービスのことである。
事業としては以前から存在したが、 に「FAST」という名称が与えられたことで理解が進み、急速に普及した。 現在はFASTプラットフォームだけで30以上、チャンネル数は3000以上あると言われている。
FASTは、コンテンツをストリーミングするという意味ではVODサービスのように見えるが、ある意味では全く逆のサービスであるとも言える。米Amazon プライムビデオや米Netflixといったサービスは、まず見たいコンテンツがあり、それを見るために加入するものだ。
一方テレビ放送は、特に何か見たいものがあるわけではないがそれっぽいものを付けていればドラマだったりお笑いだったりニュースだったりが次々にアラカルト的に流れていくので、なんとなく見たという気にさせられる。考えなくていいメディアだ。
FASTは、このテレビ的な「考えなくていい」という特性をネットに持ち込んだものと言える。プラットフォーム内には専門チャンネルが並び、それらは番組表に沿ってライブストリームでコンテンツを流し続けている。巻き戻して最初から見ることはできないが、眺めていれば次々と同じ傾向のコンテンツを流し続けてくれる。
日本で近い感覚のものは、CS放送だろう。あの専門チャンネル群がネットサービスになって、CM差し込み型の広告モデルとなり、無料で見られるといったイメージだ。
FAST事業者とビジネスモデル
FASTの事業者には、いくつかのパターンがある。大きく分けると、ハードウェア型とソフトウェア型がある。
ハードウェア型というのは、特定のハードウェアに組み込まれたサービスを指す。代表的なところでは、「ROKU」がある。ROKUはいわゆるボックス型やスティック型サービス端末の走りのようなもので、テレビをネットサービス対応にしてくれるデバイスだ。米国には同様のデバイスが色々あったが、最終的にROKUが生き残った格好だ。
「TiVo+」は、 以降に全米で流行したHDDレコーダ「TiVo」が祖業といえば祖業だが、ここは結構複雑な経緯がある。
アナログ時代にコピーガード技術を生み出した「Macrovision」が「Rovi」という番組情報配信サービス会社になり、そこに「Sonic Solutions」とか「DivX」とかが合流していってTiVoもそこに買収されたが、名前としてはTiVoの方が有名だったため社名をTiVoにした…というところまでは ぐらいまで追いかけていたが、その後はどうなったのかは取材が及ばず、正直よくわかっていない。
「Samsung TV+」はSamsungのテレビに、「LG Channels」はLGのテレビに、「Vizio Watch Free+」はVizioのテレビに組み込まれたサービスだ。
一方ソフトウェア系のほうが出自が多彩で、キー局テレビ系、ローカルサービス系、IT系などがある。キー局系としては、 にサービスインしてのちにCBSに買収された「Pluto TV」がある。ここが現在FASTの中では最大勢力である。「Tubi」はFoxが買収したサービス、「Peacock」はNBC系列のサービスだ。
IT系では米Amazonが買収した「Freevee」、クラウドサービスベンチャーからスタートした「Plex」がある。PlexはGoogle系OS搭載のプロジェクタによくアプリが搭載されているので、アイコンぐらい見たことがある人はいるだろう。これはブラウザでも視聴可能なので、どんなものか体験したい人はContinue reading...